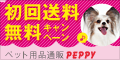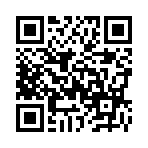2009年10月28日
灯油のバーナーはランニングコストの安さも魅力
先日アルコールバーナーについて書いた後ですが、今回は灯油バーナーのお話。
その昔、管理人が山に登ってたころ、お供の燃焼器具といえば「白灯油」を使用するシングルバーナーが定番でした。
「ラジウス」って呼んでたけど、今から思えばマナスルのものだったかも。「ラジウス」というメーカーも以前は存在してたそうだけど、消滅しちゃったブランドだそうですからね。
メーカーの名前が、白灯油のシングルバーナーの総称になってたみたい。
その後、コンパクトで、扱いも簡単なガスバーナーに取って代わられた感がありますが、気温の低いシーズンではガスよりも火力は強いし、燃料代は安上がりだし、燃料の保管は楽だし、で今でも十分使えるんですよね。別に古い、というものじゃありません。
着火の際に、プレヒートが必要だったり、ススが発生するから、バーナーのニードルクリーニングが必要だったりと使用上のコツはありますが、使い慣れてしまえば気にならないし、ランニングコストの安さと火力の強さはガスのバーナーよりも優れてます。
燃料費の安さ・燃料保管時の安全性ではホワイトガソリンよりも良いですよね。
20年以上前に使用してたのは、このタイプだったと思います。

 MANASLU(マナスル)マナスル126
MANASLU(マナスル)マナスル126

正確には違うかもしれないけど、サイズはこのくらいのサイズ。形状もこの形でしたね。卒業の時、山岳部に寄贈してしまったので定かではありませんが。
ソロで使用するにはでかくて重いけど、パーティーで使用するなら荷物の分散をすることで対応できました。
使用するときは、十分にバーナーヘッドを暖めて(プレヒート)あげないと、炎を吹き上げちゃうので、せっかちは禁物。じっくりとしっかりとバーナーを暖めてあげれば、全く問題なく燃焼してくれます。
山で使用してたのは、チューブに入ったGEL状のアルコールや、スティック状になったアルコールメタなどを使いましたね。とにかくしっかり暖めることが肝心。プレヒート剤をケチるとろくなことになりません。ちなみに、管理人は前髪とまつ毛と眉毛を焦がしたことがありますから。
最近では、登山じゃなくキャンプで使用する方も増えているようで。そんな場合は、ガスバーナーなんかで炙っちゃうっていう手もありますね。アルコールよりもガスのほうが燃焼温度が高いので、短時間でプレヒートできますからね。
ガソリンバーナーと違うのはもう1点。バーナーのニードルクリーニングという作業でしょう。ホワイトガソリンに比べると灯油はススの発生量が多いです。使い続けてると、燃料の吹き出てくるニードルにもススが溜まって燃焼が不安定になります。使う前に、付属のニードルクリーナー(ただの針ですけど)を穴に突っ込んでピストン運動させればOK。これが男心をくすぐるのかな(いろんな意味で)?
ポンピングも必須の作業ですが、これはガソリンも同じですから、ホワイトガソリンバーナーを使用したことがあれば問題ないでしょう。
このマナスルには、燃料タンクの内圧が上がり過ぎないようにする安全弁付きです。管理人は知らないんですが、昔は安全弁が付いてなかったらしいです。だから、圧力が上がりすぎないよう、気を使ったと大先輩がおっしゃってました。
火力調整もそこそこ可能です。ガスのようにとろ火も何とかこなします。ただ、あまり絞るとススがたくさん出ちゃうんですけど。
不便な面もありますが、真ちゅう製のボディやシンプルでトラブルが少なく、補修パーツも充実しているので、味のあるバーナーが欲しい、という人には灯油のバーナーもオススメできますね。燃料代を抑えたい、という向きにも灯油は安上がりですからね。
このマナスル、もう少し小さいサイズや大きいサイズもあったと思うんですが、現在ナチュラムさんでは大きい方の取り扱いがないみたい。少し小さいモデルは出てますね。

 MANASLU(マナスル)マナスル121
MANASLU(マナスル)マナスル121

ツーリングなどならこのサイズが重宝するんじゃないでしょうか。
最小モデルの96はアマゾンで扱ってました。
ソロで使用するなら良いんじゃないでしょうか。補修用パーツも十分供給されてますから、長く使えると思いますよ。
その昔、管理人が山に登ってたころ、お供の燃焼器具といえば「白灯油」を使用するシングルバーナーが定番でした。
「ラジウス」って呼んでたけど、今から思えばマナスルのものだったかも。「ラジウス」というメーカーも以前は存在してたそうだけど、消滅しちゃったブランドだそうですからね。
メーカーの名前が、白灯油のシングルバーナーの総称になってたみたい。
その後、コンパクトで、扱いも簡単なガスバーナーに取って代わられた感がありますが、気温の低いシーズンではガスよりも火力は強いし、燃料代は安上がりだし、燃料の保管は楽だし、で今でも十分使えるんですよね。別に古い、というものじゃありません。
着火の際に、プレヒートが必要だったり、ススが発生するから、バーナーのニードルクリーニングが必要だったりと使用上のコツはありますが、使い慣れてしまえば気にならないし、ランニングコストの安さと火力の強さはガスのバーナーよりも優れてます。
燃料費の安さ・燃料保管時の安全性ではホワイトガソリンよりも良いですよね。
20年以上前に使用してたのは、このタイプだったと思います。

正確には違うかもしれないけど、サイズはこのくらいのサイズ。形状もこの形でしたね。卒業の時、山岳部に寄贈してしまったので定かではありませんが。
ソロで使用するにはでかくて重いけど、パーティーで使用するなら荷物の分散をすることで対応できました。
使用するときは、十分にバーナーヘッドを暖めて(プレヒート)あげないと、炎を吹き上げちゃうので、せっかちは禁物。じっくりとしっかりとバーナーを暖めてあげれば、全く問題なく燃焼してくれます。
山で使用してたのは、チューブに入ったGEL状のアルコールや、スティック状になったアルコールメタなどを使いましたね。とにかくしっかり暖めることが肝心。プレヒート剤をケチるとろくなことになりません。ちなみに、管理人は前髪とまつ毛と眉毛を焦がしたことがありますから。
最近では、登山じゃなくキャンプで使用する方も増えているようで。そんな場合は、ガスバーナーなんかで炙っちゃうっていう手もありますね。アルコールよりもガスのほうが燃焼温度が高いので、短時間でプレヒートできますからね。
ガソリンバーナーと違うのはもう1点。バーナーのニードルクリーニングという作業でしょう。ホワイトガソリンに比べると灯油はススの発生量が多いです。使い続けてると、燃料の吹き出てくるニードルにもススが溜まって燃焼が不安定になります。使う前に、付属のニードルクリーナー(ただの針ですけど)を穴に突っ込んでピストン運動させればOK。これが男心をくすぐるのかな(いろんな意味で)?
ポンピングも必須の作業ですが、これはガソリンも同じですから、ホワイトガソリンバーナーを使用したことがあれば問題ないでしょう。
このマナスルには、燃料タンクの内圧が上がり過ぎないようにする安全弁付きです。管理人は知らないんですが、昔は安全弁が付いてなかったらしいです。だから、圧力が上がりすぎないよう、気を使ったと大先輩がおっしゃってました。
火力調整もそこそこ可能です。ガスのようにとろ火も何とかこなします。ただ、あまり絞るとススがたくさん出ちゃうんですけど。
不便な面もありますが、真ちゅう製のボディやシンプルでトラブルが少なく、補修パーツも充実しているので、味のあるバーナーが欲しい、という人には灯油のバーナーもオススメできますね。燃料代を抑えたい、という向きにも灯油は安上がりですからね。
このマナスル、もう少し小さいサイズや大きいサイズもあったと思うんですが、現在ナチュラムさんでは大きい方の取り扱いがないみたい。少し小さいモデルは出てますね。

ツーリングなどならこのサイズが重宝するんじゃないでしょうか。
最小モデルの96はアマゾンで扱ってました。
ソロで使用するなら良いんじゃないでしょうか。補修用パーツも十分供給されてますから、長く使えると思いますよ。

マナスル121と同じくらいのサイズなのが、この武井バーナーの101。別名パープルストーブの最小モデルです。
101には301のような予熱器は付いてませんので、アルコールなどでプレヒートが必要になります。
ノズルにはニードルをクリーニングする針が内蔵されているので、メンテナンスは簡単ですね。
火力はマナスルよりも強いみたいです。その分燃料消費も少し早いかな。マナスルよりもとろ火が苦手みたいですね。

マナスル126と同等のモデルがこちらのパープルストーブ301ですね。燃料タンクは126よりも大きいですが燃焼時間はほぼ同じです。
マナスルにはない、自動予熱器を備えた白灯油バーナーです。灯油を使用してプレヒートを行うのでアルコールなどは必要としません。これ、使い慣れたらかなり便利だと思います。
旧モデルからバーナーヘッド周辺が変更され、風防効果のあるバーナーヘッドになったので風が吹いても消えにくいですね。かなり進歩した灯油バーナーといえますね。

タンク容量2.8Lの最大モデルです。連続燃焼時間10時間と長時間燃焼が可能です。
ゴトクサイズが大きくなり、大き目のコッフェルにも対応できるので、この501ならファミリーキャンプにも対応可能ですね。
501には燃料タンクの圧力計が装備されてます。ポンピングの目安になる便利な装備ですね。
さすがに最大モデルなので、重量も収納サイズも大きくなってしまいますけどね。

バーナーに燃焼式ヒーターアタッチメントが付属する301セットです。
ヒーターアタッチメントをはずせば、もちろん通常のバーナーとして使用できますし、冬は暖を取ることも可能です。
このタイプの性質上、熱は上のほうにより多く回りますがホヤの中に張られたヒーターコイルで周囲にも熱は回ります。下の方への輻射熱は少ないので、テーブルなどの天板が焦げるようなことはまずないですね。

501のヒーターセットです。燃焼時間が長いのでヒーターとして使用するならこちらの方が重宝するかもしれませんね。
アウトドアグッズならこちらもオススメ
アウトドア&フィッシング厳選ストア ウェブ館

Posted by あごひげあざらし at 15:29
│キャンプ