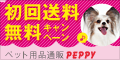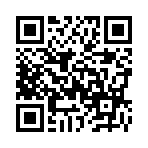2017年08月20日
避難所開設訓練に参加してきた
本日、自治会の役員として避難所開設訓練というのに参加してきました。地震だけでなく水害なども多発していいる昨今ですから、これはぜひ参加させていただこう、ということで。
参加してみると、ほかの自治会の方々含めて100名近くいたでしょうか。そしてそのほとんどの方が60歳以上と思われます。現役世代としてはうちの町内から出席した管理人を含めて2名、他町内で1~2名だけだったような。。。。。もちろん皆さん、元気な方ばかりです。避難所となる体育館まで徒歩で来られたわけですからね。一番遠い自治会では徒歩で30分くらいかかったとおっしゃってました。それができるだけの元気と体力はお持ちの方々です。
で、避難所の開設訓練とは。
まず、避難所となる建物の安全確認を行うんですね。そりゃそうです。被災した建物では危険ですし休めません。インフラの状況もわかるといいですね。電気や水道が使用できるかできないかで大きく変わりますから。危険物があれば除去してからが原則です。
ついで各自治会毎に避難してきた人の確認、できれば自宅の被災状況や家族の人数、年齢、状況、アレルギーや持病などの有無、特技や資格もわかると避難所運営に役立つそうです。看護師さんや介護師さんなどですね。個人情報なので取り扱いに注意は必要ですが、避難所では不可欠な情報です。
施設内に避難したら避難所として機能するよう整備します。利用スペースの確保、備蓄物資の配布、仮設トイレの設置、ルール作りなどですね。また市内や周辺の情報収集も必要でしょう。
避難所にはリーダーとなる人がいないと運営が難しいという話も聞きましたが、それは避難してみないとわからないことですね。優秀なリーダーのいる避難所はトラブルが少ないそうですよ。
今回初めてダンボールを使用したベッドの実物を見ました。というか、組み立てました。結構しっかりできているものですね。

小さめのダンボール箱4つで1つのユニット、このユニットを6つ使用して1つのベッドになります。強度の高さの理由の一つはこれでしょう。

小さなダンボールには筋交いのような形で段ボールの板が1枚、斜めに入ります。これが小さな箱の強度を高めてるんですね。よくできてます。これなら多少体の重い方でも安全に使用できそうです。
簡易トイレはちょっと実用性ではどうだろう?と思うものでしたね。使用後のビニール袋の処理にも困りそう。それなら下水のマンホールを開けて使用するタイプの方が良さそうです。もちろん下水が使える状況である、という条件は付きますね。
発電機はカセットガスを使用するものが用意されてました。

出力は微妙ですが、LEDの投光器に使用するなら十分な発電量です。それ以外に使用するのは難しそうですね。またカセットガスの備蓄がないそうで。カセットガス2本で約1時間発電する発電機。相当量のカセットガスを用意しないといけないでしょう。
いざとなったらみんなで持ち寄るしかないでしょうね。もしくはガソリンの発電機を調達するのがいいかもしれません。
最近はソーラーパネルもリーズナブルになってきてます。メインに使用するには発電量や夜間に発電しないなど使いにくい部分もありますが、サブ的な使い方なら十分機能しそうです。
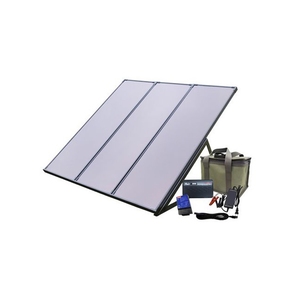
 桐生 55Wソーラー発電キット & kiryu バッテリーパック
桐生 55Wソーラー発電キット & kiryu バッテリーパック

ソーラーパネルとバッテリーのセット。
¥48157(税込) 9%割引
実際に避難所のお世話になったことのある人は皆無だった今回の訓練。避難所を使用することがあった場合、どれほどスムーズにいけるかわかりませんが、備蓄用品の置き場所等がわかっただけでもよかったです。やや備蓄品が少ないようにも思えたので、自宅や各自治会で備蓄しているものを持ち寄ることも必要でしょうね。


参加してみると、ほかの自治会の方々含めて100名近くいたでしょうか。そしてそのほとんどの方が60歳以上と思われます。現役世代としてはうちの町内から出席した管理人を含めて2名、他町内で1~2名だけだったような。。。。。もちろん皆さん、元気な方ばかりです。避難所となる体育館まで徒歩で来られたわけですからね。一番遠い自治会では徒歩で30分くらいかかったとおっしゃってました。それができるだけの元気と体力はお持ちの方々です。
で、避難所の開設訓練とは。
まず、避難所となる建物の安全確認を行うんですね。そりゃそうです。被災した建物では危険ですし休めません。インフラの状況もわかるといいですね。電気や水道が使用できるかできないかで大きく変わりますから。危険物があれば除去してからが原則です。
ついで各自治会毎に避難してきた人の確認、できれば自宅の被災状況や家族の人数、年齢、状況、アレルギーや持病などの有無、特技や資格もわかると避難所運営に役立つそうです。看護師さんや介護師さんなどですね。個人情報なので取り扱いに注意は必要ですが、避難所では不可欠な情報です。
施設内に避難したら避難所として機能するよう整備します。利用スペースの確保、備蓄物資の配布、仮設トイレの設置、ルール作りなどですね。また市内や周辺の情報収集も必要でしょう。
避難所にはリーダーとなる人がいないと運営が難しいという話も聞きましたが、それは避難してみないとわからないことですね。優秀なリーダーのいる避難所はトラブルが少ないそうですよ。
今回初めてダンボールを使用したベッドの実物を見ました。というか、組み立てました。結構しっかりできているものですね。
小さめのダンボール箱4つで1つのユニット、このユニットを6つ使用して1つのベッドになります。強度の高さの理由の一つはこれでしょう。
小さなダンボールには筋交いのような形で段ボールの板が1枚、斜めに入ります。これが小さな箱の強度を高めてるんですね。よくできてます。これなら多少体の重い方でも安全に使用できそうです。
簡易トイレはちょっと実用性ではどうだろう?と思うものでしたね。使用後のビニール袋の処理にも困りそう。それなら下水のマンホールを開けて使用するタイプの方が良さそうです。もちろん下水が使える状況である、という条件は付きますね。
発電機はカセットガスを使用するものが用意されてました。
出力は微妙ですが、LEDの投光器に使用するなら十分な発電量です。それ以外に使用するのは難しそうですね。またカセットガスの備蓄がないそうで。カセットガス2本で約1時間発電する発電機。相当量のカセットガスを用意しないといけないでしょう。
いざとなったらみんなで持ち寄るしかないでしょうね。もしくはガソリンの発電機を調達するのがいいかもしれません。
最近はソーラーパネルもリーズナブルになってきてます。メインに使用するには発電量や夜間に発電しないなど使いにくい部分もありますが、サブ的な使い方なら十分機能しそうです。
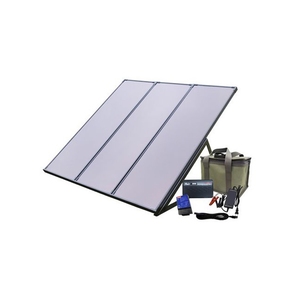
ソーラーパネルとバッテリーのセット。
¥48157(税込) 9%割引
実際に避難所のお世話になったことのある人は皆無だった今回の訓練。避難所を使用することがあった場合、どれほどスムーズにいけるかわかりませんが、備蓄用品の置き場所等がわかっただけでもよかったです。やや備蓄品が少ないようにも思えたので、自宅や各自治会で備蓄しているものを持ち寄ることも必要でしょうね。

Posted by あごひげあざらし at 23:02
│地震・災害対策など